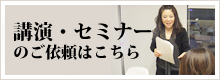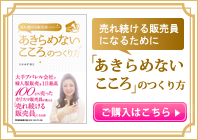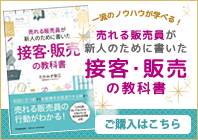- ホーム
- オフィシャルコラム
オフィシャルコラム
緊急事態宣言解除後の販売時に必要なこと
東京も、緊急事態宣言が解除されました。
実は、この1か月半で、化粧品が次々と切れてしまい、
同じものであればネットで買えるのですが、
季節が夏に向かって行くので新しい商品が欲しくなり、
本日、徐々に再開し始めているデパートのコスメカウンターに行きました。
各ブランド、テスター商品はもちろん置いておらず、
見本品には、全て透明カバーがかけられていて、手で触れられないようになっていました。
そんな中、とても感じたことがあったのです。
透明カバーがかけられていることは、感染防止のためには当然、仕方がないこと。
でも、これではお客様はとても買いづらい・・・・
では、どうしたらいいのか?
「人」が、買いにくさをカバーするのです!
つまり、販売員が商品を今まで以上に分かりやすくプレゼンすることが絶対的に必要なのです。
触れなくても試せなくても、お客様が試したかのようにイメージできるプレゼンをするのです!
当然、通常営業のようにカウンター内で販売員同士が私語をしている
なんていうのは、言語道断です。
イレギュラーな状態なのですから、販売員が店頭でどれだけ印象良く
アプローチをして、商品プレゼンを行うかが大きく問われますし、
それにより、通常営業時の何倍も結果は変わってきます。
「販売員が、店内で立っていること自体がお客さまへのパフォーマンスです」
ということは、常々講演研修でお伝えしていますが、それが、今、より一層結果を左右します。
プロの腕の見せ所ですね!
ちなみに、わたしは継続使用しているコスメを「これください」で購入ました。
その後、新しい商品を購入する気満々で物色しましたが・・・・
購入には至りませんでした。笑
残念ですね。
是非、参考にしてくださいね。
ではまた!
伝わる伝え方
部下への教え方が下手なんです!
上司が言っていることの意味が分からないんです!
コンサルティングをしていると組織の上司・部下の方々から
このようなご相談を受けることが多々あります。
わたし自身の経験を少しお話しすると、新卒入社時から
いつもリーダーをやらざる得ない環境にいて、新卒で入社して2週間経った頃から、
つまり、社会人になってからほぼ、ずっとリーダーとしてチームと組織を引率してきました。
教え方を教わったことはありませんが「みんなをまとめないと売り上げが取れない」
という危機感から、長い間、試行錯誤し徐々に教育のコツを掴んでいきました。
人に教え育てることで悩み苦しんだ中では、部下から教わることもとても多く、
そのおかげで会社員時代から独立して現在までで延べ800以上の店舗・組織、
人数にすると7万人以上の人材教育を行い、成果を出すことができました。
さて、人材教育の中で大切なことのひとつに「話しや説明していることをどれだけ相手に伝えられるか?」
ということがあります。
そこで、今日は伝わる伝え方についてお話ししますね。
伝わる伝え方のポイントは3つあると考えています。
1つ目:部下が知っている言葉に置き換える
これは、自分が説明したいことを相手がどう認識するかを考えて、
その人が使っているだろう言葉を予測して置き換える、ということです。
その年代や業種、今の相手の立場などで予測して言葉を選ぶと良いと思います。
2つ目:言葉を定義する
1つ目で予測した言葉を相手がさらに理解できるように
「○○というのは〜〜という意味ですよね」と言葉の意味を定義します。
これにより、相手により明確に伝わるのと、そこにいる全員が同じ認識になり、
より話がスムーズに伝わるようになります。
3つ目:事例を挙げる
事例はとても大切です。
但し、そこにいる人たちの背景に近い事例で話すことです。
これによりリアリティが増し、聞き手がイメージしやすくなり
より理解が深まります。
※わたしは事例を話す時にその場面をロープレで見せることも行います。
これにより、あまりにもリアリティがあり笑いや「これ、わたしです!」
などの声が挙がります。笑
「人に伝える」というのは、伝える側が自分の立ち位置に立ったまま
「あなたがわたしの言うことを理解してください」では、とても伝わりません。
また「わたしはこの経験しかないから」と自分の経験だけ話しても部下はイメージしにくく
「上司のあなただから、それでできたのよね」で終わってしまい、やる気になりません。
でも、これをやっている人、結構います。笑
人をやる気にさせ動かすには、相手の立場に立ち、相手に分かりやすい言葉で、
どれだけイメージさせるかが大切になります。
そして、実はもうひとつ伝える側が理解しておくべき大切なことをことがあります。
それは、何度も何度も心を持って伝えるということです。
1回2回言っただけでは伝わらない、ことも多々あります。
それは理解できない相手のせいではなく伝える側の問題が大きいのです。
今日は少し長くなってしまいましたが、是非参考にしてくださいね。
ではまた!
お客様と会話が続く簡単な方法
研修講演コンサルティングはアパレル販売員向けですか?
言っていることはちょっと・・・という理由のため現在も現場に立っています。
自粛期間に販売員が行うこと
・社会の一員として世の中の情勢を知る